8 シーフリード『がんを餓死させる ケトン食の威力』
- yd
- 2024年7月2日
- 読了時間: 6分
Thomas N. Seyfried
Cancer as a Metabolic Disease
On the Origin, Management, and Prevention of Cancer
John Wiley & Sons Inc.
2012
日本語全訳の要約版 作成 旦 祐介 2024年6月30日
第八章 グルタミン発酵とがん細胞のエネルギー源
無酸素のアミノ酸発酵ががん細胞にエネルギーを供給する
ミトコンドリアのアミノ酸発酵は、アザラシなどの潜水動物に見られる。低ブドウ糖と低酸素状態の心臓と腎臓でも行われている。しかし、がん細胞がオクス·フォス呼吸の代わりにアミノ酸発酵でエネルギーを得ているとは誰も気づかなかった。がん細胞はミトコンドリア内のアミノ酸発酵で基質レベルリン酸化を通してエネルギーを生産できる。ワーブルクでさえこのことは見落としていて、呼吸とブドウ糖発酵だけが細胞のエネルギー代謝手段と考えていた。
クエン酸回路の発酵が呼吸の欠陥を補えることは、酵母細胞実験で実証されている。ワーブルクはこのことに触れなかったので、彼がこの発酵ステップを通じてエネルギーが得られると自覚していたかは定かではない。グルタミン発酵は、がん細胞の呼吸不全を補填できる。
ブドウ糖の発酵はよく知られているが、アミノ酸発酵はあまり知られていない。ブドウ糖発酵では乳酸塩ができるのに対して、低酸素状態のアミノ酸発酵ではコハク酸塩、アラニン及びアスパラギン酸が副産物である。有酸素状態で乳酸塩が出てくるのは異常で、細胞が発酵していることを示す。発酵の度合い(乳酸塩生産)は、悪性増殖の度合いと相関性がある。呼吸が少なければ発酵は大きくなる。
ネズミのがん細胞のグルタミン発酵
がん細胞は、グルタミンを発酵することでエネルギーを生産できる。私たちの研究で、グルタミンだけの培養基でもブドウ糖だけの培養基でも、がん細胞は十分エネルギーを生産できた。また、グルタミンだけではほとんど乳酸塩を生産しない。培養基に高濃度ブドウ糖がある場合、乳酸塩にはほとんどグルタミン炭素が含まれないことも確認できた。
しかし、ATP合成と乳酸塩生産は、ブドウ糖とグルタミンを混合した培養基の方が著しく活発だった。このことから、ブドウ糖とグルタミンは相乗効果を発揮することがわかる。他のアミノ酸では同じ効果はなかった。
さらに、がん細胞ではミトコンドリアがグルタミンを使ってエネルギーを生産できる。そこで出た疑問は、がん細胞がオクス·フォス呼吸を使ったのか、ミトコンドリア発酵を使ったのか、という点だった。
培養基にブドウ糖とグルタミンが両方あれば、がん細胞のエネルギー代謝は順調に進む。低酸素状態もシアン化物(呼吸の阻害剤)もオクス·フォス呼吸を阻害するので、ブドウ糖とグルタミンの相乗効果がオクス·フォス呼吸によるとは考えにくい。むしろ、非酸化基質レベルリン酸化によるエネルギー合成である。
がん細胞は低酸素状態での発酵で生存できる
生物や細胞器官そしてがん細胞も、低酸素状態下での発酵作用で生存できる。つまり、ミトコンドリアのアミノ酸発酵は、低酸素状態でのオクス·フォス呼吸を補完できる。
がん細胞は、低酸素状態でグルタミンとブドウ糖を同時に発酵させられる。しかし、有酸素状態でグルタミンを発酵できるかは確認する必要がある。ワーブルク効果は、有酸素状態でブドウ糖を発酵することを指す。その時乳酸塩が生産されれば、発酵している裏付けになる。グルタミンは、低酸素状態の呼吸でエネルギーになる。高濃度のブドウ糖は、オクス·フォス呼吸を抑制するので、通常の酸素濃度でのグルタミン発酵の可能性が出てくる。通常の酸素状態で、グルタミンの呼吸と発酵を区別するのは難しい。双方ともクエン酸回路を使うからである。
低酸素状態でATPを得るには、ブドウ糖とグルタミンの発酵だけが頼りである。従ってブドウ糖とグルタミンを標的にすれば、がんのエネルギー代謝をシャットダウンできるはずである。
ワーブルクは、がんへのエネルギー供給はシャットダウンしにくいと理解していた。しかしがん細胞へのブドウ糖とグルタミンを遮断すれば、がん治療になる。第十七章で、ケトジェニック·ダイエットと、ブドウ糖·グルタミンを遮断する薬物の組み合わせで、がん細胞のエネルギー代謝を止められることを検討したい。
がん細胞が低酸素状態で生き延びられるのは、正常細胞より生命力が旺盛だから、ではなく、有機物を発酵できるからである。有機分子は、電子を受容する上で酸素の代わりになる。がん細胞は、ワーブルクが最初に示したようにブドウ糖を発酵できるが、グルタミンも同時に発酵できるかもしれない。酸素が得られるようになったらオクス·フォスに戻れる正常細胞と違って、がん細胞は酸素の有無にかかわらず発酵代謝に頼って生きている。がん細胞が発酵するのは、オクス·フォス呼吸が出来なくなっているだからである。がん細胞が発酵で生き延びるのは、がん病理学のカギである。
グルタミンの酸化とグルタミンの発酵とを区別するのは難しい。なぜなら両方ともミトコンドリア内で起きるからである。両者の違いは、発酵がATP生産と結合するかしないかである。ワーブルクが再三述べたように、ブドウ糖を全く発酵しないがん細胞は存在しない。
がんのエネルギー代謝を説明する三つの仮説
現在、私の見方では、がん細胞のエネルギー代謝に関して、三つの重要な仮説がある。第一の仮説はワインハウスのもので、がん細胞が正常な呼吸機能を持っているにもかかわらず有酸素の解糖系発酵をしているとするものである。この見解はがんの遺伝子説と一致する見解である。つまり、発がん遺伝子とがん抑制遺伝子の異常が有酸素解糖系の発酵を開始させるとしている。
この見解は、がん細胞の不十分な呼吸ががんの起源であるとする第二番目のエネルギー代謝説とは対立する。ワーブルクは、がん細胞では発酵の損傷より呼吸の損傷が頻繁であると主張した。呼吸は発酵より複雑である。なぜなら呼吸は、ミトコンドリアの複雑な構造と、解糖系発酵より回数の多い酵素の関与が必要だからである。がんでは解糖系発酵の損傷より呼吸の損傷が多い。
一つ目のワインハウス仮説を受け入れるためには、がん細胞のミトコンドリアの構造と呼吸が損傷していることを示す膨大なデータを無視する必要がある。加えて、がん細胞に正常なミトコンドリアを移植すると、がんの細胞核を再プログラムして正常な細胞に戻る実験結果も無視する必要がある。これに対して正常な細胞核とがんの細胞質から正常細胞を作ることは決してできない。こうした実験結果では、染色体ががんの起源であるとする仮説(体細胞突然変異説)は成り立たない。
第二の仮説によれば、がん細胞では解糖系発酵が呼吸を抑制する。この仮説だと、がん細胞のミトコンドリアの異常で呼吸が抑制された結果、発酵が生じる。この仮説はワーブルクの発見と符合している。
第二の仮説の発展形である第三の仮説は、ワーブルクの仮説を支持しつつ、がん細胞が呼吸の不十分を補うために、解糖系(ブドウ糖の発酵)に加えてミトコンドリアでの発酵も使ってエネルギーを得ていると見なす。これがシーフリード研究チームの有力な見方になっている。
章のサマリー
がんは異常なエネルギー代謝の病気である。がん細胞は、呼吸が不十分になってもなんとか生き残るために、発酵でエネルギー代謝をおこなっている。発酵することで、がん細胞は酸欠状態でも生存できる。




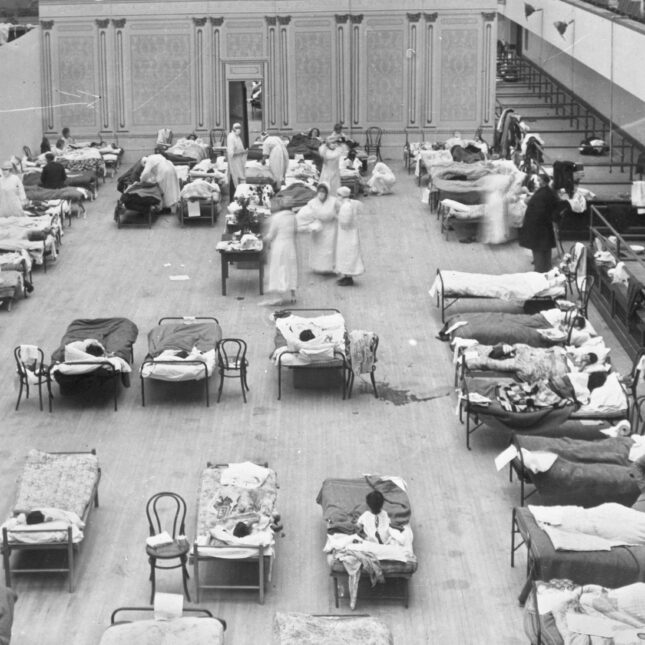


コメント