6 シーフリード『がんを餓死させる ケトン食の威力』
- yd
- 2024年7月2日
- 読了時間: 6分
Thomas N. Seyfried
Cancer as a Metabolic Disease
On the Origin, Management, and Prevention of Cancer
John Wiley & Sons Inc.
2012
日本語全訳の要約版 作成 旦 祐介 2024年6月30日
第六章 ワーブルク論争
がん研究において、ミトコンドリアの役割ほど熱心に議論されてきたトピックはない。私はこの論争をハル·ヘルマンの「偉大な対立」のリストの医学か科学の項に入れたいくらいだ(Hal HellmanはGreat Feuds in Science: Ten of the Liveliest Disputes Ever, Wiley, 1999年において、一七世紀から二〇世紀の代表的な十の科学論争を紹介した)。ミトコンドリアに関するこの論争は、がんが細胞の呼吸の損傷から生じているとするオットー·ワーブルク博士の強い主張から始まっている。ミトコンドリアは、「食べ物からエネルギーを得るとき酸素を消費する」という細胞の呼吸を担当している。ワーブルクは、一旦細胞ががん化したら呼吸は正常には戻らないと強調した。彼はさらに、呼吸ができなくなると言っても細胞が死ぬほど深刻なことにはならない、なぜならがん細胞は死んだ細胞からは発生しないからである、とも言った。
がん細胞の呼吸が困難になっている証拠ははっきりしている。なぜなら酸素はオクス·フォス回路(細胞の呼吸)でのエネルギー代謝(ATP合成)に不可欠だが、多くのがん細胞では酸素の消費が激減するからである。しかし、一部のがん細胞では酸素消費は減少しないどころか、悪化するにつれて酸素消費が増大するがん細胞もある。しかしこれは、呼吸が正常であるという証拠にはならない。ワーブルクは、増大する酸素消費が必ずしも呼吸及びATP生産に繋がっているとは限らないと考えた。つまり彼は、一部のがん細胞は酸素を消費し二酸化炭素を出すが、それは呼吸に使われるのではなく、結果としてエネルギー代謝は不十分なままであると考えた。
(がん)細胞のミトコンドリア内膜が損傷すると、ATP生産が止まり、発熱が進む。がん細胞が発熱すると増殖も早まる。がん細胞の発熱は調整できない。
ミトコンドリアでATP生産が低下すると、別のエネルギー代謝方式が必要になる。ワーブルクは、ブドウ糖を乳酸にする発酵が、がん細胞のエネルギー代謝の代替メカニズムであると強調していた。がん細胞では、この発酵を大幅に拡大する必要がある。呼吸エネルギー代謝が減少すれば、他の何かエネルギー代謝方法が不可欠である。補完的方法がなければ細胞はエネルギーの欠乏で死ぬ。がんの起源に関するこの単純な仮説がどうしてそんな論争の的になってしまうのか。大部分の研究者は、解糖系(発酵)の向上はほとんど全てのがんのエネルギー代謝の特徴であると理解しているにも関わらず、損傷した呼吸によってがん細胞で解糖系が増強することががん細胞の原因であり起源でもある、というシンプルな事実を受け入れられないでいる。
シドニー·ワインハウスのワーブルク理論批判
シドニー·ワインハウスは二〇世紀の著名ながん研究者で、がん研究誌の編集者を務め、全米がん研究学会の理事でもあった。オットー·ワーブルクが一九五六年の論文をサイエンス誌に掲載したすぐあと、ワインハウスは「編集長への手紙」と題する一文を出版し、がん細胞は呼吸障害があるとするワーブルクの基本的な見方を批判した。論争はワーブルクの反論、及びディーン·バークとアーサー·シェイドの議論で過熱した。
ワインハウスは、ワーブルクの死後六年経った一九七六年の論文で、ワーブルクの仮説をさらに痛烈に批判した。この論説で最終的にがんの呼吸障害に関する論争が終結し、損傷した呼吸の重要性は後退し、遺伝子の変異に注目が移った。しかし二一世紀の現在、この問題は再びがん研究の主眼となっている。
当時ワインハウスは、がん細胞で酸素消費も二酸化炭素生産も両方とも高いから、呼吸は損傷していないと考えていた。もしがん細胞の呼吸が決定的に損傷していたら、どうして酸素を消費し二酸化炭素を生産できるのか。彼は、多くのがん細胞が脂肪酸を代謝してエネルギーにできるから、二酸化炭素を排出すると考えたのだった。加えて彼には、パスツール効果(酸素があると発酵が抑制される効果)もがん細胞で正常に見えた。というのは、がん細胞で、酸素が乳酸の産出を減らしたからである。ワインハウスは、ミトコンドリアの傷害を示す証拠はないと考えていた。
これに対して、当時すでにピーター·ペダセンががん細胞のミトコンドリアにいくつも異常があることを突き止めていた。さらにワインハウスと同僚たちは、実際にワーブルク理論を裏付けるデータを収集していた。悪性肝臓がんで、高い呼吸が明確に分化したがん(つまり肝機能を保持していて、がん化の度合いが低い細胞)によく見られるのに対して、ミトコンドリアの喪失を伴う低呼吸は機能分化していないがん(増殖や転移性がある細胞)に見られることもわかっていた。この結論はワーブルクの中心的な仮説に沿った結論である。私は、当時のがん学会が、ワーブルク理論に関するワインハウスの不正確な説明を安易に受け入れていたことが不思議でならない。
ワーブルクは、ワインハウスに対する一九五六年の反論の中で、驚くほど簡潔だが含蓄のあり滑稽な回答を出している。「がんの問題はライフを説明することが目的ではなく、がん細胞と正常な成長細胞との違いを見つけることが目的である。幸いなことにこれは、ライフが本当は何なのかを知らなくても解明できる。二つのエンジンを想像してほしい。一つは石炭の完全燃焼、もう一つは不完全燃焼で動くエンジンである。エンジンの構造や目的について何も知らない人でも違いは発見できるだろう。例えばその人は臭いを嗅ぎ分けるかもしれない」。言い換えれば、石炭燃焼が不完全な場合、大気中には硫黄が検知できる。ブドウ糖燃焼が不完全な場合、乳酸がミクロ環境で検知できる。ワーブルクはがん細胞において呼吸が損傷していることを知っていたのである。
ワーブルク理論に基づく治療法を確立するために、がんのメカニズムを完璧に解明する必要はない。
まとめ
ワーブルク理論の論争は、多くのがん細胞で見かけ上呼吸が正常で、且つ、一部のがん細胞で呼吸機能を回復できるとする観察結果から生じている。がん細胞が正常な呼吸をしているように見えるなら、どうしてワーブルクが主張したように呼吸の障害ががんの原因と言えるのか、というわけである。
ワーブルク本人の言葉遣いが混乱の一因になったのかもしれない。ワーブルク理論を批判するワインハウスの論文が引き続き引用されているのを見ると、多くの研究者は議論を注意深く読まず、データをきちんと評価していない。ワーブルクはがん細胞の呼吸が正常であるとは一言も言っていない。
ワーブルク理論の長所と短所は、読者が自ら判断してほしい。呼吸の不足ががんの最重要な特徴である。誰か、呼吸に有利な環境で、正常細胞とがん細胞の呼吸に差がないというエビデンスを示して私に反論してほしい。私たちの実験では、正常細胞を高ブドウ糖培養体から、脂肪·ケトン体を含む低ブドウ糖培養体へ移動できたが、同じことをしたら、がん細胞は全部死んだ。正常な呼吸能力のある細胞は低ブドウ糖状態へのこの移行に耐えられるが、がん細胞は移行できない。もしがん細胞の呼吸が正常なら、ケトン体·脂質を利用できるはずである。呼吸できる正常細胞はケトン体を活用してエネルギーを得られるが、呼吸機能が損傷したがん細胞はケトン体を活用できない。
がん細胞の呼吸の損傷が幅広く受け入れられるまで、がんの治癒は進まないだろう。逆にこの理解が広まったら、新しい治療方法が開発され、悪性腫瘍は進行しなくなり、患者は長生きできるようになるだろう。




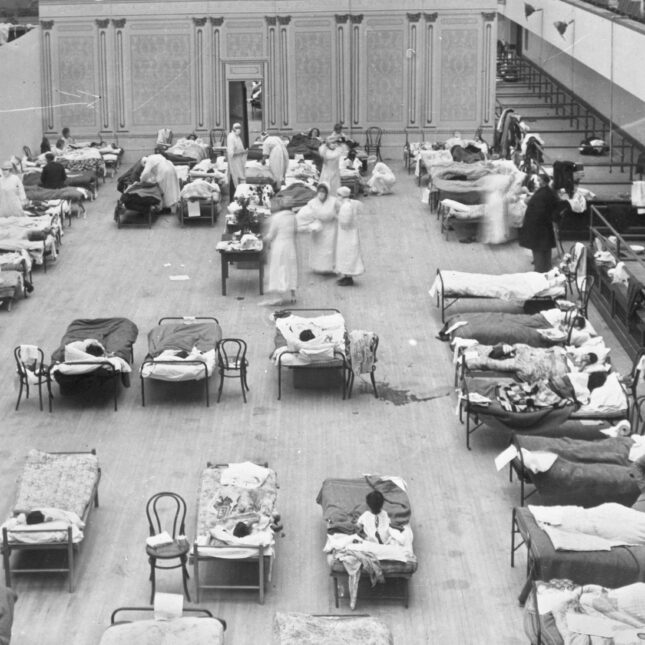


コメント