4 シーフリード『がんを餓死させる ケトン食の威力』
- yd
- 2024年7月1日
- 読了時間: 9分
Thomas N. Seyfried
Cancer as a Metabolic Disease
On the Origin, Management, and Prevention of Cancer
John Wiley & Sons Inc.
2012
日本語全訳の要約版 作成 旦 祐介 2024年6月30日
第四章 正常細胞とがん細胞のエネルギー源
細胞が生きて活動するにはエネルギーが必要である。エネルギーの大半はATP(アデノシン三リン酸)というリン酸塩として貯蔵され、必要に応じて加水分解で活用される。これはATP加水分解と呼ばれ、細胞のエネルギー代謝にとって最も重要なことである。
ATP加水分解による自由エネルギーは、全ての細胞活動の源である。細胞において、エネルギーの大半は、カルシウムなどを出し入れするイオン膜ポンプを動かすことに使われる。細胞のサバイバルには、ありふれたこのポンプが一番エネルギーを必要としている。
エネルギー代謝の恒常性
生命体は安定した状態を維持する傾向がある(恒常性)。イオン膜ポンプへのエネルギーが途切れると、細胞は膨れ上がってしまう。ナトリウムとカルシウムのイオン濃度が高まり、カリウムのイオン濃度が下がって、細胞内外のバランスが崩れるからである。エネルギー源のATPがすぐ入手できれば恒常性は保てるが、エネルギーがポンプへ行かなくなると、細胞全体が不具合になり、やがて器官や生命体全体が機能不全に陥る。
ATPの合成方法は複数ある。哺乳類の正常細胞ではミトコンドリアが大半のエネルギーを生産する。ほとんどが酸化的リン酸化(オクス·フォス)という仕組みで生産される。このATP生産方法を細胞の「呼吸」と言う。これが全細胞エネルギーの八九%にあたる。これらの方法はがん細胞でも機能するが、がんの種類によって活発さに差が出る。
ATPを作る酵素の効率は、ミトコンドリア内膜の脂質比率に大きく左右される。細胞膜の内側と外側との浸透圧の差を維持することは、ミトコンドリアにとって極めて重要である。
オクス·フォス(酸化的リン酸化、呼吸)と並んで、全細胞エネルギーの約十一パーセントは「基質レベルリン酸化」で作られる。これは、発酵とも言う。発酵によるATP合成にはさらに二つの方法がある。一つは解糖系と言う発酵過程を使ってブドウ糖からピルビン酸を作る。二つ目は、クエン酸回路のスクシニルCoAシンテターゼ反応によるものである。スクシニルCoAシンテターゼ反応は、無酸素状態で、より効率的にエネルギーを供給できる。この経路もがん細胞で重要なエネルギー源になる。
通常は、解糖系からATP分子二つが生産され、ミトコンドリアでのスクシニルCoAシンテターゼ反応からも、同じくATP分子二つが生産される。酸素を使うオクス·フォス反応と対照的に、基質レベルリン酸化で酸素は要らない。研究の結果、がん細胞は低酸素状態でもエネルギーを産み出し生き延びられることがわかった。
もしオクス·フォスだけでエネルギーが不十分な場合、クエン酸回路の細胞基質レベルリン酸化過程を増やす必要がある。これは、オクス·フォスが減少した時、解糖系を通したATP分子数を増やす適応と似ている。
驚くべきことに、どの器官の細胞もエネルギーの強さは同じだった。安静時細胞膜能力がバラバラな心臓·肝臓·腸の細胞のエネルギーは同じ強さだった。さらに、心臓と肝臓はオクス·フォスでエネルギーを得るのに対して、腸細胞は完全に解糖系のみだった。つまり、エネルギー消費と生産のバランスは、どの細胞も変わらなかった。
正常細胞もがん細胞もエネルギー量が同じ高さで安定していることは、細胞エネルギー恒常性にとって重要である。このエネルギーバランスが狂うと、細胞の機能と生存が危うくなる。
但し、腫瘍内のエネルギーの精密な測定は困難である。測定しようとすることで細胞内部に変化が起きるからである。正常細胞は、基質レベルリン酸化と呼吸を通じてエネルギー消費と生産をバランスさせる能力があるが、がん細胞はエネルギーをうまく調整できない。
細胞は、エネルギーが少なすぎても多すぎても死滅する。エネルギーが少なすぎると壊死するか計画的な死になる。多すぎると、呼吸と生存を抑制することになる。
オクス·フォス(細胞の呼吸)活動が急激になくなると、細胞膜ポンプエネルギーがなくなり、細胞の計画死あるいは壊死につながる。エネルギー不足が軽微であれば、細胞は基質レベルリン酸化(発酵)によるエネルギー代謝を増強し生き延びることができる。但し、変化に順応できるようになるまで時間がかかる。
長い間発酵でエネルギーを調達していると、細胞はなんとか生き延びようとして、ゲノムの変異や増殖や転移で対応するようになる。呼吸が不十分で発酵も増やせないような細胞はやがて死滅してしまうから、がん細胞には決してならない。発酵で生き延びられる細胞は、損傷したミトコンドリアに頼る必要がなく、且つ、細胞の老化や死滅をバイパスできる。老化をバイパスする細胞だけががん化する。
正常細胞とがん細胞のATP代謝
ワーブルクは、ネズミのがん細胞を使って、呼吸より発酵のエネルギー代謝の方が多いことを確認した。その後の研究でがん細胞は、呼吸で二五%しかエネルギーを代謝していないことがわかった。
ブドウ糖発酵によるエネルギー代謝
ワーブルクは、細胞の呼吸機能が損傷したあと生き残るために、細胞ががん化してブドウ糖と解糖系(発酵)で生き延びることを初めて明らかにした。彼は、呼吸と発酵だけが全ての細胞のエネルギー代謝手段であり、エネルギーだけががん形成を左右すると考えていた。彼は、「呼吸と発酵について、この二つが細胞のエネルギー代謝反応であり、この二つがATPを合成でき、それによって生命体がエネルギーを得られることだけ知っていれば十分である」と主張した。
ワーブルクは、発酵とは、酸欠状態でブドウ糖から乳酸を形成することと理解していた。酸素濃度が低いとピルビン酸が乳酸に還元される。乳酸発酵の酸化過程は、基質レベルリン酸化に先立つ反応である。これができないと細胞は生存できなくなる。
乳酸は、ブドウ糖の不完全な酸化で発生する老廃物であり、細胞の周辺環境からできるだけ早く除去する必要がある。ひとたび酸素が入手可能になると、パスツール効果によりブドウ糖利用と乳酸生産が低下する。
パスツール効果は、細胞や微生物による解糖や発酵が、酸素によって抑制される現象である。嫌気性バクテリアは酸素がなくても発酵できるが、酸素があれば呼吸もできる。酸素がある状態で乳酸生産を伴うブドウ糖発酵のことを後になってワーブルク効果と言うようになった。ワーブルク効果とは要するに、好気性ブドウ糖発酵、または酸素のある状態での持続的乳酸生産のことである。がん細胞にはパスツール効果は当てはまらない。ワーブルク効果は当てはまる。
ワーブルクは、がん細胞の有酸素発酵が呼吸の不具合のせいであると考えた。有酸素状態で死滅するがん細胞なら、嫌気性細胞と見なせるかもしれない。この現象に関する私(シーフリード氏)の見解は、基本的にワーブルクと同じである。がん細胞は有酸素状態でブドウ糖を発酵し続ける(有酸素解糖系、またはワーブルク効果)。なぜならがん細胞はオクス·フォス(呼吸)で十分なATPを生産できないからである。従ってワーブルク効果は、呼吸の不具合から始まる。がん細胞が効率よく呼吸できるなら、非効率な発酵でエネルギーを増産する必要はない。
ワーブルクは、がん細胞がミトコンドリアでアミノ酸を発酵させることを理解していなかったようだ。ミトコンドリアのアミノ酸発酵は、がん細胞がまるで通常の呼吸をしているかのように見えるので、誤解を招く。この点がワーブルク理論を取り巻く批判に繋がった可能性がある。
がん細胞は、酸素のある状態でブドウ糖発酵を行い、その副産物として乳酸を蓄積する。そして、ミトコンドリアでアミノ酸(グルタミン)からATPを生産できる。
正常細胞はエネルギーの需給バランスの取り方が上手だが、がん細胞はミトコンドリアが不具合なのでエネルギーの需給バランスがうまく取れない。有酸素発酵(解糖系)はがん細胞特有のエネルギー代謝方法である。有酸素呼吸で十分なATPを生産できるようながん細胞は存在しない。
がん細胞は、クエン酸回路のあるミトコンドリアで呼吸しているように見えるかもしれないが、オクス·フォス(呼吸作用)によるATP合成はしていない。この見かけ上の呼吸は、アミノ酸発酵である。ブドウ糖とグルタミンは相乗効果を発揮して、がん細胞の発酵を進める。
呼吸できなくなったがん細胞は、乳酸の代謝を伴うブドウ糖の活用を進める。がん細胞でエネルギーバランスが損なわれているのは、酸素欠乏状態でもATP生産を抑制しないからである(9)。がん細胞は低酸素状態で逆にATP生産を増やしているように見える。
がん分野で、呼吸とワーブルク効果が最も激しい論争の的になっている。がん細胞の種類によっては低めのブドウ糖条件で、特にグルタミンも存在する場合に、呼吸が高まるかもしれない。
乳酸塩代謝の有無でのグルタミノリシス
アミノ酸の一つであるグルタミンは、細胞の呼吸が不具合の時、クエン酸回路でATPを発生させる。がん細胞も、グルタミンでエネルギーを生産できる。さらにグルタミンは、がん細胞の転移を推進するので、グルタミンを標的にすれば転移を大幅に抑止できる。
グルタミノリシスとは、グルタミンが酸化経路を使って二酸化炭素とピルビン酸と乳酸塩を生産する過程である。
37 がん細胞では、グルタミンから乳酸がほとんど生産されない。ところがグルタミンにブドウ糖を加えると乳酸がたくさん生産された。がん細胞でのグルタミンからの乳酸塩生産問題はまた決着がついていない。
TCAサイクル、基質レベルリン酸化
グルタミンはスクシニルCoAを形成する。スクシニルCoA合成は、酸素がなくても基質レベルリン酸化でATPを製造できる。この反応により低酸素状態または高血糖状態にある細胞で大規模なATP合成が可能である。ミトコンドリアのグルタミン発酵とクエン酸サイクルの基質レベルリン酸化が、転移がんを生存させられる。
コレステロール合成と低酸素状態
コレステロールは主要な細胞膜脂質である。がん細胞はこれを必要としているが、わざわざ合成しなくても、低酸素状態の血清から直接コレステロールを獲得できる。だからネズミのがん細胞は、発酵する燃料とコレステロールがあれば低酸素状態で成長できる。
サマリー
細胞はエネルギーが必要である。正常細胞はエネルギーの大半を呼吸で生産するが、がん細胞は発酵で獲得する。発酵は、細胞質内の解糖系とミトコンドリア内のサクシニルCoaシンセターゼとで発生する。がん細胞のミトコンドリアは呼吸しているように見えるが、私たちはこれは擬似呼吸と呼んでいる。なぜならがん細胞でオクス·フォス[呼吸]は不活発だからである。がん細胞は、発酵燃料とコレステロールがあれば、酸欠状態でも発酵で生き延びられる。呼吸が正常細胞のエネルギー的特徴であるのに対し、発酵こそががん細胞の特徴である。酸素の有無にかかわらず発酵ががん細胞を生かし続ける。悪性がん細胞は呼吸ではなく発酵で生き延びる。だから発酵過程を阻害すれば、がんは予防も治療もできる。




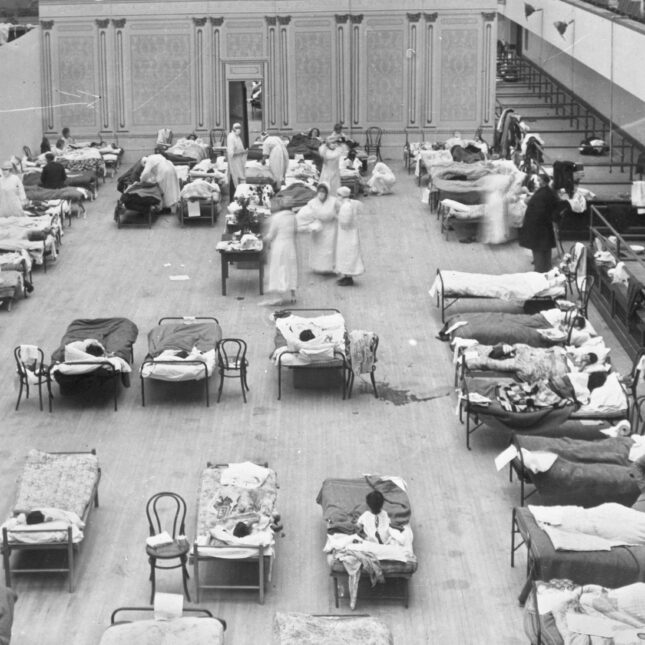


コメント