2 シーフリード『がんを餓死させる ケトン食の威力』
- yd
- 2024年7月1日
- 読了時間: 6分
Thomas N. Seyfried
Cancer as a Metabolic Disease
On the Origin, Management, and Prevention of Cancer
John Wiley & Sons Inc.
2012
日本語全訳の要約版 作成 旦 祐介 2024年6月30日
第二章 がんがどうしてできるかに関する混乱
多種多様ながんを統合的に把握する理論がないため、私たちの理解が遅々として進まない。現在、がん研究者はがんが遺伝子の突然変異の病気[Cancer as a genetic disease]と見なしている。細胞のDNAの損傷により、正常細胞が死に至るがん細胞に突然変異するという説明である。
半世紀以上、がん研究と薬物開発を支えてきたこの遺伝子突然変異説は、今日、批判の的となっている。重大な不整合があり、そのせいでがんゲノム·プロジェクトは効果的な治療法につながっていない。
がんは、実は遺伝子の突然変異がきっかけになって発病するわけではなく、細胞のエネルギー代謝の異常による病気[Cancer as a metabolic disease]である。がんとは欠陥細胞のエネルギー代謝の病であって、その結果ゲノムが損傷している。
私は、細胞の呼吸系の損傷が発生した結果として、がん細胞の遺伝子的欠陥が生じる証拠を見せたい。がんの損傷したエネルギー代謝システムを標的にすることで、低コストで毒性のないがん予防·管理ができるようになる。
がん化の逆説
がんのそもそもの原因は、放射線、化学物質、ウイルスあるいは炎症など数多くあるが、引き金はどうであれ、正常細胞ががん細胞になるプロセスは単一の共通のプロセスである。多種多様な原因からがん化というシンプルな単一の現象が始まるので、昔から「がん化の逆説」と呼ばれている。
現在主流の仮説によれば、がんは、次の六つの特徴があるとされている。
一 がんの無規制の成長は、成長を制御する遺伝子の異常から始まる。
二 がん細胞の抑制遺伝子やミクロ環境が壊れることで異常な増殖が始まる。
三 がん細胞は計画的な細胞死(アポトーシス)に向かわなくなる。
四 がん細胞は無制限に増殖できる。
五 がん細胞は血管新生を促進する。
六 がん細胞は転移する。
シーフリード氏は特に一と二に根本的な異議を唱えている。
ゲノム的不安定さ
現在主流のこの考え方によれば、ゲノムが不安定なのでがんが六つの特徴を持つ。つまりがんが遺伝子の病であるとしている。しかし、ふつう、遺伝子が変異する速度は遅いので、がん細胞の何百万もの遺伝子変異が、人間が生きているうちに突然多数起きるとは考えにくい。またゲノムを保護する役割の遺伝子が、どうしていともたやすく変異してしまうのかも説明できていない。
ワーブルク効果
酸素がある状態での発酵(有酸素発酵、有酸素解糖系)のことをワーブルク効果と言う。これは全てのがんに共通のエネルギー獲得方法である。がん細胞においてはミトコンドリアが損傷しているので、細胞の呼吸とエネルギー代謝が不調である。そこで、がん細胞は酸素がある状態でブドウ糖を発酵させ、エネルギーを生産してサバイバルを目指す。
全てのがんに共通の遺伝子変異や染色体の異常はない。逆に、全てのがんに共通するのは有酸素発酵である。これを発見したドイツの化学者オットー·ワーブルクは、生化学と細胞生理学のパイオニアとして、一九三一年に酵素の業績で生理学·医学のノーベル賞を受賞している。
ワーブルクは、がん細胞がミトコンドリアによる呼吸(エネルギー代謝)ができなくなった場合、サバイバルのために、有酸素のブドウ糖発酵(有酸素解糖系)を行うことを発見した。彼は当時、次のように説明している。「ペスト病には、高熱、昆虫、ネズミなど数多くの引き金があるが、共通する原因はペスト菌だけである。それと同じように、がんの発生には数多くの遠因としてタール、放射線、ヒ素、圧迫やウレタンなどがあるが、がんの共通特徴のは一つしかない。呼吸系の不可逆的な損傷である」。
正常細胞の無酸素発酵とがん細胞の有酸素発酵の違いは、正常細胞の無酸素発酵が酸素の欠乏時に生じるのに対して、がん細胞の有酸素発酵は、酸素はあっても呼吸ができない時に生じる。正常細胞では、呼吸活動が進むため、酸素が無酸素発酵と乳酸の生産を抑える(有酸素時の発酵阻害、パスツール効果)。これに対して、がん細胞は有酸素状態でも乳酸を作り続けてエネルギーを得ようとする。なぜなら、がん細胞はミトコンドリアでのエネルギー代謝ができないからである。
ワーブルクは、呼吸系統が損傷しても、解糖系を使ってエネルギーを得られる細胞だけががんになる、逆に、解糖系を活性化できない細胞はエネルギー不足で死滅する、正常細胞ががん化するのは、ミトコンドリアによる呼吸ができなくなるためである、と理解していた。シーフリード氏の研究グループはこのワーブルクの概念に加えて、がん細胞が、「アミノ酸の発酵回路」及び「クエン酸回路」でもエネルギーを生産すると理解している。
ワーブルクはがんの原因が呼吸系の損傷であると主張し、当時、がん研究者の間で大論争を引き起こした。ワーブルク理論は、単純過ぎるし、一見がん細胞が正常そうに見える呼吸活動をしている理由を説明できないとして攻撃された。ワーブルクも当時の学界も、がん細胞がタンパク質を活用できるとは理解していなかったらしい。
がんが遺伝子の病であるとの考え方は、化学的発がん物質や放射線がDNAを損傷するとする証拠とも合っていたので、論争の結果、「遺伝子損傷の病としてのがん」という見方が優勢となり、「代謝異常の病としてのがん」という見解は影が薄くなった。
再評価
現在主流のがんの理解によれば、ゲノムの突然変異こそがワーブルク効果とがん細胞のエネルギー代謝の障害をもたらしている。つまりがんの異常なエネルギー代謝は、がん遺伝子とがん抑制遺伝子の欠陥により生じる結果に過ぎないと見なされている。しかし、シーフリード氏はこの見解に異議を唱えている。新たな実験でがんの遺伝子起源説には疑問符がつき、がんがエネルギー代謝の病と見ている。
DNAを発見したジェイムズ·ワトソンが、最近になって、がんのエネルギー代謝についてもっと研究すべきだと発言している。本書では、あらゆるがんが呼吸·エネルギー代謝の損傷から生じていると主張したい。細胞の呼吸の不足が先にあって、その結果としてゲノムの不安定が生じている。
ミトコンドリアが損傷した結果、がん遺伝子が損傷する。細胞核のゲノムは細胞質にあるミトコンドリアが十分呼吸しているかどうかで決まる。細胞は常にエネルギーを必要としている。ワーブルクは、がん細胞が一見普通に呼吸しているように見ていて、実はミトコンドリアの呼吸が損傷していることを明確には説明できなかった。私は、損傷したエネルギー代謝がどうがんの予防と管理に活用できるか説明し、オットー·ワーブルクの考えを補強したい。




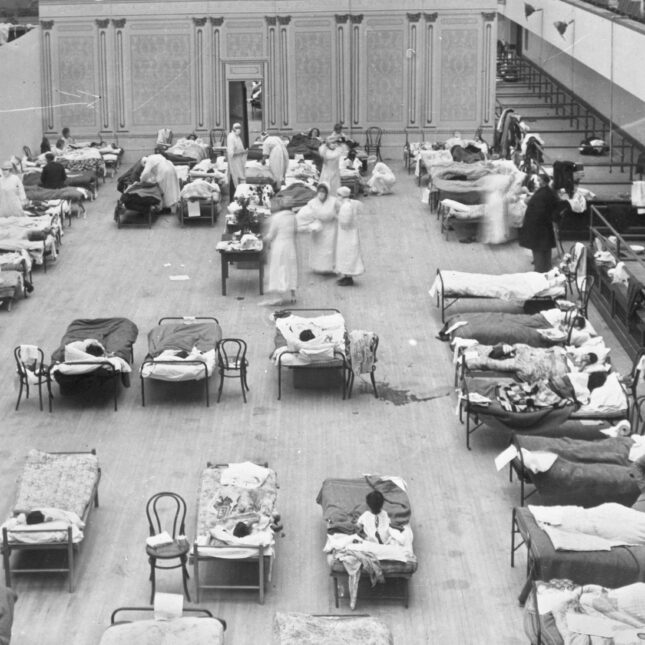


コメント