17 シーフリード『がんを餓死させる ケトン食の威力』
- yd
- 2024年7月2日
- 読了時間: 29分
Thomas N. Seyfried
Cancer as a Metabolic Disease
On the Origin, Management, and Prevention of Cancer
John Wiley & Sons Inc.
2012
日本語全訳の要約版 作成 旦 祐介 2024年6月30日
第一七章 がんのエネルギー代謝的管理
がんはエネルギー代謝の不具合の病気なので、治療はがん細胞のエネルギー代謝を標的にするべきである。この戦略は、あらゆるがんに適用できる。なぜなら全てのがんが共通の不具合、つまり細胞呼吸が損傷し発酵に頼らなければならない事情があるからである。ブドウ糖とグルタミンを制限することにより、がん細胞の周辺環境を変えることを説明したい。食事制限は代謝療法の一つで、数多くのがんの成長を顕著に遅らせられる。食事制限は当然血糖値を下げるが、がんは血糖に頼って生き延びている。全てのがん学者は、がんが食事制限を目の敵にしていることを知るべきである。この治療法は、診断直後で患者がまだ元気な時に最も効果的である。
この章では、食事制限療法(Dietary Restriction Therapy)と表現する。がん治療の効果は、身体にエネルギーを提供する食物を減らす点にある。食物からエネルギーが来なくなると、体は体内に貯蔵してある脂肪とタンパク質からエネルギーを生産するようになる。炭水化物は、これらの分子から合成される。人類は、長期間食物がなくても効率よく活動できるように進化してきた。治療のためのファスティングで、体は新たなエネルギー代謝状態に移行する。呼吸不全とゲノムの不安定のせいで、がん細胞は新エネルギー代謝状態に移行できない。
食事制限は、栄養素全体の減少のことで、飢餓との違いは、食事制限が栄養失調を引き起こさずに総カロリー摂取を減らす点である。自然療法としての食事制限は健康を回復させ、がん形成を防ぎ、炎症を減らす。カロリー摂取を減らすことは、それまでの治療法に悪影響を与えることなくがんを抑制する。ファスティングは、化学療法の悪影響も減らせる。がんの成長は、アミノ酸の制限によっても抑制される。
がん成長を減少させるのは食事内容か食事構成か
食事制限によるがんの抑制は、食事内容よりカロリー制限に比例する。単純な食事制限ががんの成長と転移を阻害する。脳腫瘍に対する食事制限は、解糖系を標的にする薬物と併用した時著しく高まる。
制限したケトジェニック·ダイエット(KD-R、制限ケトン食)は、食事制限と似た抗がん効果がある。量を減らせば、高炭水化物ダイエットでも高脂質·低炭水物ケトジェニック·ダイエットでも脳腫瘍の成長を抑制できる。
食事制限に際して、体重を指標とする方が適切である。ケトン食(ロー·カーボ)のカロリー二〇%減は、ハイ·カーボ·ダイエットの二〇%減に比べて、体重減少が少なかった。脳腫瘍の成長は、食事の栄養組成より熱量に比例する。ロー·カーボ·高タンパク質食ががんの成長を遅らせ、発がん性を減らす。ブドウ糖と体重の減少は、がんの成長の減少と関連している。体重と血糖値の減少が見られることから、効果はカロリー制限の成果である。
ネズミと人間の食事制限と治療的ファスティング
脳腫瘍が食事制限で縮小するのは、低ブドウ糖·高ケトン体の食事の時である。ケトン体(ベータ·ヒドロキシ酪酸[beta-OHB]とアセト酢酸)は、ブドウ糖が減少した時、代替燃料となる。超低カロリー·ダイエットや水だけファスティングがこれに当たる。酢酸もケトン合成の副産物だが、エネルギーとして使われるわけではなく、呼気や尿に放出される。ケトン体は、体内でアセト酢酸になるが、アセト酢酸より先に体内に取り込まれる。
ケトン食
ケトジェニック·ダイエッツ(ケトン食)は、子供のてんかん発作を管理するために開発されたが、脳腫瘍の管理にも効果的であり、ブドウ糖を抑えて低量で投与されると特に効果がある。ケトン食で血糖値が下がるのは、この食事が美味しくなくて自主規制してしまうせいである。さらに、ケトン食が高脂質組成であるため全体の消費が減少する。腸内細胞は
高脂質に対応するためにコレシストキニンを分泌する。コレシストキニンは食事行動を阻害するため迷走神経系の感覚神経細胞を活性化する。ネズミに食事制限して少ない食物を与えたところ、血糖値が下るとともにケトン体レベルが上昇した。「脂肪」対「炭水化物·タンパク質」が四対一のケトン食は、脳腫瘍マネジメントに最適である。この比率四対一は全てのがんに有効である。ブドウ糖を減らすことで、有酸素解糖系とペントース·リン酸経路の発酵によるエネルギー源を標的にしてがん細胞を攻撃する。これらは、がん細胞にとって極めて重要なエネルギー源である。
ケトン食は、ネズミの脳腫瘍の成長と血管新生を減少させたが、これは体重も減少させるくらい少ない量で投与した場合だけであった。ケトン食は、自由裁量で摂取した時や、量を制限しなかった場合[脂肪比率が多くても炭水化物とタンパク質の絶対量は多くなる]では、がん成長に対して治療効果がなかった。ケトン食を制限なしに摂取したネズミの血糖値は高い。血糖値が高いと体重は維持されるか増加する。ケトン食を無制限で投与すると、血糖値は高いままで、ケトンは大半が尿から排出される。しかしがんのあるネズミの血中ケトン値は、食事制限した方が明らかに高かった。食事制限の時ケトン体は尿で排泄されず体内で代謝に使われるために確保される。がんマネジメントの代謝的治療法を採用する時に、この情報は決定的に重要である。
ネズミの神経膠腫細胞は、ケトン食を量の制限なしに与えた場合にも成長が阻害される。一部のがんはカロリー制限(CR)やケトン食でも、敏感に成長が阻害されるのかもしれない。しかしケトン食の抗発がん性は、食事量を制限した場合に最大の効果をもたらす。無制限の摂取は高脂肪の副作用が出る。こうした副作用はケトン食の量を制限した場合には出ない。
カロリーを制限したケトン食の少量摂取は血糖値を下げる。しかしケトン食を無制限に摂取したネズミの血糖値は下がらない。つまり、血糖値を下げるのは食事の組成ではなく、食事の量である。多くの人がこれをよくわかっていない。ロー·カーボ·ダイエットなら血糖値が下がると勘違いしている。これは明らかに間違いである。
ケトン(ベータOHB)値は、標準食のネズミよりケトン食のネズミの方が高いものの、ケトン食を少量だけ摂取したネズミの方がさらに高い。少量のケトン食を食べたネズミの方がケトン値が高いのはなぜか。答えは簡単だ。ケトンは血糖値(ブドウ糖レベル)が低いと体内に保持されるからである。ケトンはブドウ糖の代替燃料である。ケトン食でカロリー無制限のグループのように、血糖値が下がらない場合、ケトンは尿から排泄される。だからケトーシスを測る場合は、尿のケトン値より血中ケトン値の方が正確である。がん細胞は低血糖でケトン値が高くなると、エネルギー不足のストレス状態になる。ケトン食の治療効果は、血糖値が低い時に大きい。
食事制限はブドウ糖を減らしケトン体を増やすが、これは正常細胞では、ミトコンドリア呼吸機能とグルタチオン酸化還元状態を改善する。グルタチオンは、細胞と組織を活性酸素損傷から守る。がん細胞で増加する活性酸素は、DNA、脂質及びタンパク質を損傷する。ケトン体も正常細胞を攻撃的ながんから守る。従って、少量のケトン食摂取による血中ケトンの自然の上昇は、がんなどの悪影響を減らせる。なおケトン体の代謝は、炎症も減らせる。
グルカゴンとインスリン
ホルモンのグルカゴンは、血中ケトン体濃度を上昇させる。グルカゴンは食事制限中に上昇すると同時に、貯蔵されているタンパク質と脂肪からブドウ糖を合成しやすくする。ケトン体はゆっくりブドウ糖に代わって脳その他の組織の主たる燃料になっていく。ケトン体は低血糖状態でも脳が通常の機能を維持できるようにする。ケトン体に加えて、貯蔵されていた中性脂肪から放出される脂肪酸が、脳を除く体組織の主な燃料になる。脳だけは低血糖状態でもケトン体を使い続ける。
食事制限中、臓器は、残ったわずかなブドウ糖を脳に回すために、ブドウ糖の利用を減らす。ラットの脳は少量の脂肪酸を代謝できる。ただし脂肪酸を活用すると発熱があるので、脳の正常な機能を邪魔する。脳は頭蓋骨に囲まれているので、放熱が難しい。ケトン利用より脂肪酸利用の方がさらに発熱しやすい。ケトン利用の方が発熱ロスが少ないので効率が良い。いずれにせよ食事制限中に脂肪酸とケトン体を代謝燃料として使うのは、十分なブドウ糖を肝臓と膵臓で合成できないためである。
グルカゴンはインスリンと反対の働きをする。食事を減らすと、グルカゴンが増え、インスリンは下がる。摂取した食物から得られたブドウ糖はインスリンを増やし、ブドウ糖の摂取を強め、細胞と組織で解糖系を強化する。インスリンが解糖系を刺激すると、ブドウ糖と解糖系に依存するがんの成長も刺激する。食べないと血中のインスリンレベルが下がるのは、血糖値が低くなるからである。つまり、食物があればインスリンは上がりグルカゴンは下がる。食物がなければインスリンは下がりグルカゴンは上がる。
基礎代謝率
基礎代謝率(BMR)は休息中に、体の体温、血流、細胞呼吸、器官活動を維持するのに必要なエネルギーのことである。人間とネズミとは基礎代謝が異なるので、食事制限に対する生理学的反応が異なる。ネズミの基礎代謝率は人間より七倍大きい。従って、食事制限に耐える能力は、人間の方がはるかに大きい。ネズミで四〇%の食事制限ですむのに、人間ではとても低いカロリー(四〇〇~五〇〇kcal)または水だけの治療的ファスティングが必要になる。制限ケトン食で低血糖を維持しながらケトン体レベルを増大させるのも可能である。制限ケトン食は過酷なファスティングの代わりになる。補足として、ケトン・エステルを用いて、血中ブドウ糖とグルタミンを下げながらケトンを上げることができる。
ケトンとブドウ糖
正常なミトコンドリアの呼吸能力のある細胞だけがケトン体を利用できる。というのは、ケトン体の活用には、電子輸送チェーンもミトコンドリア酵素も必要だからである。ブドウ糖とグルタミンがない場合、ケトン体だけではがん細胞が生存できない。さらに、ケトン体は、神経膠腫のような細胞では、ブドウ糖があっても有毒である。人間とネズミのがんは、ベータOHB(ケトン)をアセチルCoAに変換する重要な酵素がない。そもそもがん細胞は、成長や生存のためにケトン体を効率よくは使えない。これはどのがんにも当てはまる。ブドウ糖を減らしケトン体を増やす治療法は、ブドウ糖に依存するがん細胞を飢餓状態におきながら、正常細胞は保護しエネルギーを供給し続けることができる。これができるような従来型のがん治療法は存在しない。
ケトン食による脳腫瘍の治療
一九九五年、ケトン食を使った初めての人間の悪性脳腫瘍の治療法が実施された。患者の栄養状態を維持しながら、がんのエネルギー代謝を混乱させるためにエネルギー源をブドウ糖からケトン体にシフトさせる実験で、がん細胞に呼吸欠陥があるとするワーブルクのがん理論を実際に検証するものだった。もしがん細胞に呼吸の欠陥があるなら、ケトン食は治療効果があがるだろう。というのは、呼吸不全の細胞はケトン体を使えないからである。逆に、呼吸が正常なら、ケトン食に切り替えてもがんの成長に何も影響がないだろう。しかし、ワーブルクが触れたように、呼吸不全のないがんは存在しない。
ネベリング博士らの研究は、切除できない末期の脳腫瘍の二人の女児が対象だった(ステージIIIとIV)。これは画期的な研究だった。人間のがんに初めてケトン食療法が使われたからである。最初の患者は三歳の女児で、毎日八種類の極めて有毒な投薬を受けてきた。その後、頭と背骨に放射線を浴びた。子供は痙攣をおこし、広範な血液と腎臓毒性に苦しんだ。がんは悪化し続けたので、標準治療法は中止された。二番目の患者は八歳半の女児で、六歳の時に診断された初期のがんが悪性化した段階だった。抗がん剤シスプラチンの中毒で難聴になった。広範な放射線と化学療法にも関わらず二人ともがんは残っていた。二人とも長くは生きられないと考えられていた。
ネベリング博士は、中鎖中性脂肪のケトン食を使った。放射線と化学療法から深刻な生命を脅かす副作用が起きていたが、ケトン食は二人の子供に驚くほどよく効いて、化学·放射線療法なしに長期にがんの管理ができた。ブドウ糖の摂取でがんは二一·八%減少した。この治療に関するネベリング博士のコメントは、本書第二〇章を参照してほしい。
この研究から、中程度に制限されたケトン食が脳腫瘍の解糖系エネルギー代謝を減少させることがわかった。さらに、ケトン食と治療的ファスティングが大人の女性患者の神経膠芽種の成長を管理できた。ケトン食は生活の質を改善することができる。第一八章で説明するように、食物量を制限したケトン食をブドウ糖·グルタミン阻害剤と併用したら効果はもっと上がるだろう。ケトン食はよく受け入れられていて、子供と大人の悪性腫瘍患者にとって、効果的で且つ有毒でない治療法である。ブドウ糖に依存するあらゆるがんに効果があると言える。
ブドウ糖はがんの成長を加速させる!
ブドウ糖はがん細胞の解糖系の燃料となり、グルタミン酸合成だけでなくペントース·リン酸経路の前駆体も提供する。実験室でがんの成長は血糖値に比例する。血糖値が高ければ高いほどがんの成長は早い。血糖値が下がればがんの大きさ(重量)と成長率も下がる。すでに述べたように高血糖は、人間の脳腫瘍を悪化させ、悪性がんを急増殖させる。脳腫瘍の患者の結果は、脳腫瘍ネズミの研究結果と同じだった。がん専門医が治療中の患者にどうして高カロリーの飲食を薦めるのか理解に苦しむ。ブドウ糖はがんの成長を加速させる!
ブドウ糖はインスリン
ブドウ糖は血中インスリン濃度を上下させる。血糖値が上がればインスリン濃度も上がる。ただ食べ物の匂いを嗅いだり食べ物を見たりするだけでインスリンが上がることもある。インスリンは解糖系と細胞内エネルギー代謝を推進する。ブドウ糖はがんの成長をコントロールするが、加えてインスリン様成長ファクター1 (IGF-1)もコントロールしている。IGF-1は急速ながん成長にリンクする表面受容体である。IGF-1とがんの成長が連動するのは血糖値が高いせいである。食事制限はインスリンレベルを下げるとともに、IGF-1レベルも下げる。これは食事制限が血糖値を下げるからである。ブドウ糖はがん細胞のエネルギー代謝を推進する一方、IGF-1もがん細胞の成長を進める。この信号経路を遮断すればがん細胞を標的にできる。食事制限はIGF-1を減らし、アポトーシスを高める。食事制限すれば脳腫瘍でこの経路をたたくことができる。
細胞のエネルギーをブドウ糖からケトン体へ変更するには、いくつもの遺伝子レベルの変更と調節が必要だが、正常細胞でこれは簡単に起きる。これが、進化の過程で食料制限に耐えられるようにする適応方法だからである。正常細胞では、ブドウ糖の利用と解糖系の遺伝子が抑制される一方、細胞呼吸の遺伝子は強められる。それに対してがん細胞は、呼吸が不十分で、ゲノムが不安定で適応力に乏しいので除去されることになる。
がん細胞は解糖系を強める事態に直面すると、極めて強いエネルギー代謝のストレスを受ける。がん細胞は、ケトン体からエネルギーを取り出すことができないからである。ケトンを増やしながらブドウ糖を減らす治療は、がん細胞にストレスを与える。従ってケトン体へエネルギーをシフトさせるのは合理的ながん治療戦略である。
食事制限は血管新生を妨げる
血管分布はがんの増殖を左右する。がんの悪性度と侵襲性は血管分布に比例する。血管が少ないがんの方が予後は良い。血管分布を阻害するとがんをコントロールできる。どうすれば、患者に危害を加えず、また生活の質を落とさずに血管新生を狙い撃ちにできるか、が難しい。
食事制限は血管新生を遅らせてがんの成長を阻害することがわかっている。ブドウ糖不足もがん細胞の増殖、血管新生及び炎症を減らす。
ネズミの脳腫瘍の成長は、緩い形の食事制限で、八〇%も抑制された。実験二二日間の体重減少はわずか一二パーセントに止まった。緩やかな食事制限で普通のがんの成長が抑制されたが、脳腫瘍でも同じ結果が得られた。ケトン食の食事制限も血管新生を抑制するが、その効果は食事の組成ではなく量に関連している。
食事制限は脳腫瘍の血管新生を標的にしつつ、正常細胞の健康と活力を高めるので、血管新生を抑えるには、食事制限やカロリー制限したケトン食の方が、薬物治療法より優れている。食事制限はがん細胞の周辺環境全体を攻撃する。
食事制限は異常ながん血管を標的にする
がん周辺と正常組織とでは血管の構造と機能が異なる。食事制限で生じたケトーシス状態で、正常なラットの脳では毛細血管の密度が増大したが、腫瘍ラットの血管は漏れやすく成熟しない。食事制限はがんの血管分布を減らす。
がんの血管が成熟すると、そこへの治療薬の配送が楽になる。従って、食事制限や制限されたケトン食は異常ながん血管を標的にしつつ、正常な血管分布を強める。これは将来治療に応用できる。
食事制限はアポトーシスを助ける
食事制限は、アポトーシスを通じてがん細胞を殺す。アポトーシスは、普通の炎症に伴う壊死とは異なる。アポトーシスは壊死に比べて、がんの周辺環境にあまり影響しない。食事制限はがん細胞をアポトーシス的に殺すので組織の炎症が少ない。これに対して、化学療法と放射線治療は炎症と壊死を引き起こす。有毒な治療薬と、毒性のない食事制限で殺すのとどちらが良いか。私は後者を好む。
私は、組織的エネルギー制限が人間の悪性腫瘍でアポトーシスを強めると確信している。食事制限のアポトーシス促進効果は、解糖系エネルギーの減少から起きる。食事制限はエネルギーを枯渇させ、がんに酸化ストレスを与えることでがん細胞を殺す。食事制限はがん細胞には酸化ストレスを与えるが、正常細胞に対してはケトン体の上昇を通じて酸化ストレスを減少させる。有毒な治療薬だけで治療するのと、食事制限のような害のない治療法も検討するのとではどちらが良いか。病気に関心のある患者はこの議論に参加したいと思うだろう。
がん細胞はアポトーシスに抵抗力があるか。解糖系からのエネルギーが減少すれば、がん細胞は死ぬか成長が止まる。ブドウ糖とグルタミンへのアクセスが制限されると成長できなくなる。がん細胞のブドウ糖·グルタミン依存ががんの「アキレス腱」である。
食事制限は、正常細胞を温存したままがんの解糖系システムを標的にできる自然な治療法である。制限されたケトン食は、脳からのグルタミン輸出を強めるので、がんがグルタミンを入手できなくなる。ケトン·エステルを追加した食事制限は、幅広いがん細胞のエネルギーを標的にするシンプルで害のない治療法になりうる。
食事制限は炎症を抑える
炎症はがんを発生させるとともに進行も促す。炎症によってミトコンドリアが損傷し細胞呼吸ができなくなるのががんの起源である。がん細胞ではある種のタンパク質が多く分泌されるようになり、グルタミンを分解し、がんを進行させる。また、ブドウ糖を減らしケトンを増やすと、がんの炎症を抑えられる。
がんの薬で、炎症と血管新生を標的にしながら、がん細胞を殺せるものはない。食事制限はミクロ環境で炎症を標的にするシンプルな方法である。
がん学者とがん患者は、水だけの治療的ファスティングは、がんのミクロ環境で炎症を減らす方法であることを知るべきである。この治療法はファスティングが終わってからも、カロリー制限ケトン食などの治療法や治療薬によって継続できる。カロリー制限ケトン食は、エネルギー代謝を狙い撃ちする治療薬と併用すると、さらに劇的に効果が高まる(後述)。
末期がん患者のエネルギー代謝を標的にする
がん細胞の移植の直後に食事制限を開始すると、がんの進行は抑えられる。遅く始めた食事制限でも、がんの悪性化は遅くなり、生存期間が著しく伸びた。食事制限が特殊な信号経路を標的にすることで、がん細胞のアポトーシスを促す。がん治療薬業界は、がんマネジメントのためにこの経路をターゲットにしてほしい。食事制限は、高価で有毒な治療薬なしにこの経路を狙い撃ちにできる。がん患者とがん専門医はこのことを知るべきである。
食事制限は、ATP生産をコントロールする酵素を減らす。繰り返しになるが、ワーブルク効果は、ワーブルク本人が元々予想したように、ミトコンドリア呼吸の不全から生じる。がん細胞の遺伝的·エネルギー代謝の欠陥は、発酵を伴う呼吸不全にリンクしている。
食事制限に伴う解糖系の減少により、正常細胞の活性酸素濃度は減少し、がん細胞の活性酸素関連の細胞死は増加する。低血糖状態で、正常細胞はケトン体からエネルギーを得るようにシフトする。ケトン食は正常細胞で活性酸素を減らすので、神経保護の役割がある。食事制限はがん細胞に必要なブドウ糖を減らす一方、正常細胞に必要なケトン体を増やすので、食事からのエネルギーが不足しても正常細胞は生き延びられる。
エネルギー・ストレスに対する正常細胞とがん細胞との反応
食事制限しない場合、がん細胞の方がはるかに活発にブドウ糖を活用して高血糖を維持し、がんの成長を早める。食事制限した場合、ブドウ糖関連のタンパク質は、がん細胞では減るのに対して、正常細胞では増加する。つまり、そのタンパク質は、ブドウ糖を活用する上で、がん細胞と正常細胞とで逆方向に作用する。もしがん細胞が健康で適応力もあったら、食事制限下でブドウ糖が足りなくなるから、そのタンパク質がもっと増えるはずである。しかしがん細胞は適応力がないので、タンパク質を減らす。
正常細胞かがん細胞かによって、エネルギー・ストレスに対する反応に差がある。食事制限下でそのタンパク質を増やせる正常細胞の方が、ブドウ糖を多く入手できる。ケトンを活用できる正常細胞の方が、エネルギー・ストレス状態下で、より健康でいられる。正常細胞はエネルギー・ストレス下でも生き延びられるように進化してきた。
呼吸不全とゲノム不安定のあるがん細胞は健康的でない。呼吸不全が生じているので、生き延びるために発酵エネルギーに依存する。ブドウ糖が入手できなくなり解糖系が使えなくなる。発酵燃料が少なくなった時、がん細胞は健康的だとは言えなくなる。実験でも、がん細胞の方が頑丈で有利だとは確認できない。
成長を促進する物質IGF-1が減るのは、がん細胞には死活問題だが、正常細胞に害はない。食事制限で、解糖系に依存するがん細胞はアポトーシスになるが、正常細胞は死なない。これもエネルギー・ストレス下でがん細胞が不利である証拠である。総じて、ブドウ糖からケトン体へエネルギー源がシフトすると、細胞呼吸が良好な正常細胞は保護されるが、遺伝子欠損と呼吸不全のがん細胞は攻撃の的になる。がん専門医と患者はこのことを知っているだろうか。
食事制限は侵襲を抑える
悪性腫瘍の管理が難しいのは、それが臓器その他の組織を侵しやすく(侵襲性が高い)、すぐ転移するからである。ネズミの脳腫瘍は培養するととても侵襲的で、人間の脳腫瘍と同じく、転移しやすい。制限されたケトン食は、侵襲的な脳腫瘍を管理できる。
食事制限はカロリー制限の形で、ネズミの小脳腫瘍の侵襲を減らせる。食事制限したネズミのがんは境界線が濃くくっきりしていて、周辺への侵襲が見られない。
腫瘍内のがん細胞の割合及び血管数は、食事制限したネズミで顕著に少なかった。カロリー制限が、増殖と血管新生を抑制したわけである。食事制限ががん細胞の増殖も侵襲も阻害することが分かる。侵襲はがん患者の主な死因なので、食事制限により生存率が高まると考えられる。
侵襲的な神経膠芽種に対して、食事制限の治療効果と抗がん剤ベバシズマブの治療効果は対照的である。この抗がん剤はがん細胞を減少させず侵襲は増大させるようだ。人間では食事制限の方がより効果的な血管新生を抑える治療法と言える。さらに、食事制限は、下痢その他の副作用がなく、むしろ一般的な健康を促進する。食事制限の分子的メカニズムはまだ解明されていないが、食事制限が侵襲を抑制するのは、増殖、解糖系の活動、炎症及び血管新生が減少したせいである。
成長部位とがんの進行
がんが発生するのはどこか、発生するのは人間か動物かは、食事制限の治療効果に影響するかもしれない。食事制限は、ネズミのがんと人間の脳腫瘍が成長できないようにする。食事制限が脳腫瘍に効かない事例は経験していない。
有意義な実験を行うためには、同じ動物の同じ部位でがんを育てることが大切である。確かにがんは糖尿病のネズミに移植すればよく育つだろうが、食事制限との関係を調べる時は、糖尿病でないネズミを使うべきである。
抗がん治療のための食事制限
ネズミ脳腫瘍の私たちの実験結果は、抗血管新生·抗がん治療と食事制限を併用しようとする場合に参考になる。食事制限しながら血管新生を阻害する薬の効力を調べるにあたり、体重もがん成長も減った場合、それが薬だけの効果であることを確認する必要がある。
新薬の評価には比較対象群を設定することが重要である。著名な研究者の実験でも、味覚異常·筋肉痙攣·体重減の比較グループがないので、治療効果が阻害剤のせいか阻害剤の副作用のせいかわからないことがある。もし全ての治験が比較対照グループを設定していたら、米国食品医薬品局(FDA)は、がん新薬をほとんど認可できないだろう。新がん治療薬の科学論文は、必要な比較対照集団を実験計画に入れていない。これは深刻な問題である。
ブドウ糖を標的にする
食事制限は特殊な信号経路を断つことで、がん細胞の増殖を抑え、アポトーシスを進め、血管をできにくくする。解糖系に関わる遺伝子も抑制する。これによってがん細胞のサバイバルが困難になる。加えて、クエン酸サイクルの機能を制限し、解糖系依存を増強する。だから食事制限はいくつもの方法で効果をもたらし、且つ有害でないエネルギー代謝療法である。どうして多くのがん学者がこのコンセプトを理解できないのか。
食事制限の他、イマチニブやレスベラトロールなどがん細胞のエネルギー代謝を標的にする薬がいくつもある。しかしいずれも有毒性が問題で、高い用量を投与する必要があって副作用が強い。
食事制限は血糖値を下げるのに有効だが、血中ケトン値への影響についてさらに研究が必要である。エネルギー源としてケトンを使わないままブドウ糖が低下すると、脳に悪影響があるが、食事制限で、がん細胞は効果的に殺しつつ、ケトンを活用して低血糖時に脳を保護できる。
メトフォルミン
糖尿病治療薬のメトフォルミン(グルコファージ)は、患者の血糖値を下げるために広く使われている。メトフォルミンは肝臓の酵素を標的にすることで血糖値を下げる。血糖値を下げることから、がん細胞へのブドウ糖を制限するのに使えないか検討されている。
制限ケトン食と解糖系阻害剤の併用
食事制限はがんの成長と侵襲を減らすが、悪性腫瘍を完全に抹消できるわけではない。ブドウ糖代謝を標的にする薬と組み合わせることになる。解糖系阻害剤と制限的ケトン食との併用で、がん細胞の成長を抑制できる。これは、ATPを枯渇させ、がんの細胞死を誘発するからである。カロリー制限を模倣する薬は、食事制限と併用すべきである。模倣剤は、グルタミンを抑制する薬との併用でさらに効果があるだろう。
ファスティングと食事制限は、化学療法の効果を高め、副作用を減らせる。食事制限を抗解糖系薬と併用すると、がん細胞は急速に死滅する。単独だと効果のないカロリー制限模倣剤でも、ケトン食と併用で効果が高まるので、治療薬開発の新しい道を開拓できる。患者支援団体は、治療薬と食事療法を併用する臨床試験を要請するべきである。
制限ケトン食と高酸素療法
制限ケトン食と高圧酸素療法(HBO)の組み合わせはどうか。HBOは一ないし二気圧の酸素一〇〇%での治療である。HBOは生体組織内酸素を増やし、怪我の治療だけでなく、肺がん、乳がん、及び神経膠腫の治療に使われてきた。多くのがん細胞が高酸素に反応するようだ。HBOはがん細胞のミトコンドリアを「爆発」させ、グルタミン発酵に依存しているがん細胞は殺せる。
高圧酸素療法は、食事制限と同じく、がんの血管新生を攻撃しながら、がん細胞のアポトーシスを促進する。HBOは炎症も標的にする。
高圧酸素療法も制限ケトン食も、がんの解糖系を標的にする。制限ケトン食がブドウ糖を得にくくする一方、HBOは解糖系の酵素を叩き、ワーブルク効果を推進することになる。
がん細胞は呼吸機能不全のため、過剰な活性酸素を持っている。制限ケトン食はがん細胞の活性酸素を増加させるのに対し、高圧酸素療法も活性酸素を高め、がん細胞死のリスクを高める。一方ケトン体は、普通細胞を活性酸素の損傷から守る。制限ケトン食とHBOの組み合わせは、正常細胞を傷つけることなくがんを破壊できる新しい治療法になる。
グルタミンを標的にする
食事制限と抗解糖系がん治療薬は、解糖系とブドウ糖に依存するがんに効果があるが、グルタミンに依存するがん細胞にはあまり効果がない。グルタミンは多くのがん細胞の主要なエネルギーとなるアミノ酸で、特に肝臓と骨髄の細胞はグルタミンに大きく依存する。骨髄細胞は転移がんの起源なので、がん治療上、対策は重大事である。さらに、グルタミンは、栄養失調により衰弱した状態に関わるサイトカイン(免疫細胞からのタンパク質)の合成に必要である。グルタミンを抑えることは転移がん治療にとって重要であるが、これまで、ネズミでグルタミンの実験はされていなかった。
人間で血中グルタミン濃度を下げるためには、特殊な酸を使ってグルタミンを尿から排泄する。ネズミ実験ではDONという抗生物質を使った。DONはグルタミンの分解を止める。結腸と肺のがんの患者に使うと、がんの成長を遅らせられる。DONがグルタミンを阻害することで転移がんを減らせる治療薬になる。
グルタミンの標的化は組織的転移を阻害する
がんのあるネズミを使って、グルタミン阻害薬DONと食事制限でがんの転移に影響があるか調べた。何も投与せず食事制限もしない比較対照グループ、DON投与グループ、食事制限グループ、DON·食事制限併用グループのうち、DONを投与したネズミの体重は比較グループのと変わらなかった。血糖値はDONグループと比較グループで大差なかった。しかし食事制限グループの血糖値は顕著に低かった。
DON・食事制限併用グループでは、がんのサイズが小さくなったが、抗がん効果はDONの方が食事制限より勝っていた。食事制限だけでは転移は防げなかった。
むしろグルタミンが転移を促進しているのではないか。適度な身体活動は血中グルタミンを増やすので、食事制限下で餌を漁りまくるネズミは身体活動を高め、その結果血中グルタミンが上がる可能性はあった。がん細胞はマクロファージと共通点があるが、グルタミンはマクロファージを含む免疫細胞の主たるエネルギー源である。変身したマクロファージやその融合ハイブリッド細胞は転移がん細胞になる。従って、グルタミン制限が転移を減少させるか確認するのは重要なことだった。
実験の結果、グルタミン阻害薬DONは肝臓、肺、腎臓への転移を防いだ。肝臓への転移は比較対照グループの全てのネズミに見られた。肝臓は人間の転移がんが多く発生する臓器である。DONを投与したネズミの肝臓にはがん細胞がなかった。
興味深いことにDONネズミグループは脾臓への転移があった。脾臓は、骨髄細胞に似た転移細胞がある。
DONは人間には使えるが、一部の実験ネズミには有毒だった。DONは肝臓、肺及び腎臓への転移を減らしたが、生存率は低かった。DON治療は、単独でも食事制限との組み合わせでも、顕著にがんの成長と転移を減少させた。さらに、DONと食事制限の組み合わせでは、DONを減らしても、DON単独より抗がん効果があった。
DON+食事制限のネズミは期間中活発で健康な体重も維持した。DON単独のネズミは、体重が減り、最後の三日間無力になるなど副作用が大きく、実験が進むにつれて、有毒性が明らかになった。DONとカロリー制限併用の方が有毒性が少なく、生存も良好だった。併用の場合少ない用量の投与で済んだせいだろう。脾臓への転移も併用組が顕著に少なかった。DONその他のグルタミン阻害薬は、食事制限や他のブドウ糖阻害薬との併用治療は有望である。
DONは、人間の方が転移の抑制に効果的ではないか。DONでグルタミンを制限すると、ブドウ糖の活用が活発になるが、制限ケトン食でブドウ糖はカットするので問題は発生しない。グルタミンを標的にするのは転移がんの強力な治療法になりうる。
食作用を標的にする
白血球が異物を破壊したり、死滅した細胞を除去したりする「食作用」は、転移がんにも見られる。乳がん細胞はイースト細胞を飲み込んだあとアポトーシス状態になる。イースト細胞ががん細胞にアポトーシスをもたらす。
黒色種細胞の食作用は、低ブドウ糖状態で顕著に増加する。これは転移細胞が栄養不足の時に食作用を「食べさせる」方法として使っている可能性がある。食作用を狙えば転移を減らせる。
食事制限は血糖値を下げるが、ネズミでは転移は減らなかった。食事制限はマクロファージ食作用を増加させる。食事制限が転移細胞の食作用を強め、がん細胞へのエネルギー·ストレスを減らした。がん細胞は、ブドウ糖を含まない最低限のマトリゲル培養基で育てると、乳酸を作る。マトリゲルなしだと乳酸を作らず細胞は死んだ。このことは、マトリゲル培養基ががん細胞のために発酵によってエネルギーを作ったことがわかる。
抗マラリヤ薬のクロロキンはオートファジーを減らせるかもしれない。患者を食事制限状態に置けば、クロロキンその他の抗食作用をさらに強めることができる。
ミクロ環境を標的にする
一部のがんは治らない傷のような振る舞いをする。ミクロ環境はがん細胞を抑制している。けがを治すためのサイトカインは、実は逆に炎症を強めがんを進行させる。傷の修復過程は、さらにがんを増殖させる。
食事制限は炎症を鎮める。ブドウ糖からケトン体に切り替えるのも、がんのミクロ環境において炎症を強く抑制する。この理由から、ケトン食は炎症による数多くの神経的·神経変性的疾患に使用できないか検討されている。
食事制限はがん細胞とがんのミクロ環境を同時に標的にする治療法なので、がんの進行を遅らせられる。食事制限ほど幅広く数多くのミクロ環境の炎症を抑制できる治療方法はない。患者とがん·コミュニティが認識すれば、がんのマネジメントは大きく前進できる。
ミトコンドリア強化療法としての食事エネルギー低減療法
私はこれまで、がんの食事療法を「食事エネルギー低減」(DER: dietary energy reduction)と呼んできた。これは食事制限という表現より好ましい。すでに病気で十分苦しんでいるがん患者は、制限されることを望まないからである。制限という言葉は治療に対する後ろ向きなアプローチを想像させる。「食事エネルギー低減」ですらそうである。もっと前向きな名称はないかと考えているうちに、ミトコンドリア強化セラピー(MET: mitochondrial enhancement therapy)という名称も悪くないと思うようになった。
ブドウ糖からケトン体代謝へのシフトは組織炎症と活性酸素を減らしながら、ミトコンドリアのエネルギー代謝効率を強める。METは食事制限に関わる用語を排除しているので、人間のがん·マネジメントの用語として魅力的である。さらにMETはこの治療法の実際のメカニズムを説明している点で、より正確でもある。METは、やがて人間のがんを管理し予防する最も効果的な治療戦略として認められるようになるだろう。
サマリー
この章では、細胞のエネルギー代謝を狙い撃ちにすれば、がんの増殖が抑えられることを示した。全てのがん細胞はエネルギー処理能力に共通の欠陥があるので、その欠陥を狙い撃ちにする治療法が有効である。オクス·フォス呼吸ができなくなったがん細胞は、サバイバルのために発酵回路に大きく依存する。だから発酵を標的にする治療法はとても有効である。がん細胞を叩くために正常細胞も活用できる。がん細胞は呼吸できず発酵しかできない。従って、正常細胞は脂質を活用して呼吸している間に、がん細胞だけを絶滅させられるのである。




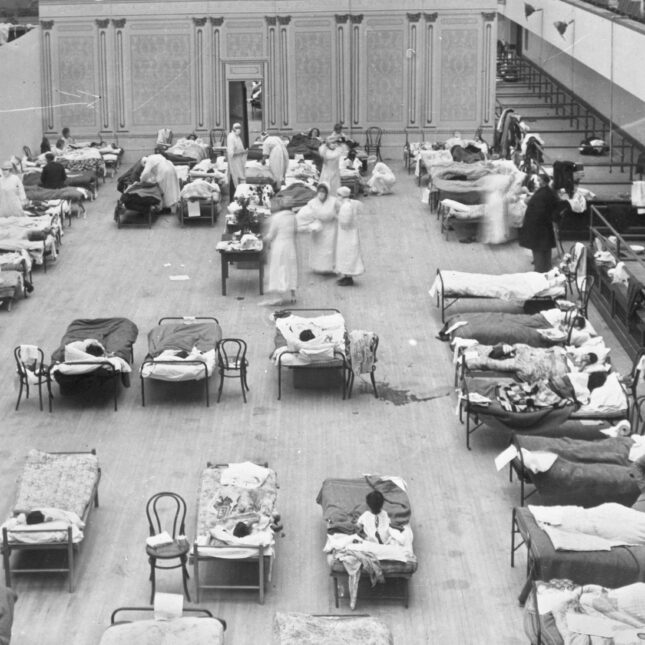


コメント