ある学長に対する辞表の強要 A university president in Japan forced to resign for no reason
- yd
- 2022年12月5日
- 読了時間: 6分

大学におけるパワーハラスメント事例として、以下の日本の某私立大学元学長の学校法人理事会宛て挨拶文を掲載します。掲載許可は得てあります。大学側は契約に基づき支払うべきだった未払いの学長手当の一部を和解金として支払うことに同意しました。これは、地位回復や名誉回復という観点からははなはだ不十分な結末でありながら、法律の専門家の見地からは悪くない原告勝訴の成果と言えるとのことです。
学校法人理事・評議員・監事宛ての経緯説明(個人情報は伏せ、文意をわかりやすくするためごく一部分修正してありますが、その他は2022年3月末の提出の文章です。)
全文
すでに理事会・評議員会で報告があったかもしれませんが、ご心配をおかけした当事者の皆様に、謹んでひとことご挨拶申し上げます。
学長職に就いて3年目、コロナ禍の2020年10月に、私は、理事長から突如辞表を書くように言われました。辞表を書かなければ臨時理事会を開催して解任すると通告されました。9月に某副学長が理事長に手紙を出したことは知っていましたが、それは就任したばかりの副学長の主観的で事実誤認に基づく意見でしたから、理事長には書面および面会にて、きちんと説明してありました。それまで学務運営に関して理事長から警告を受けたこともなければ、調査委員会が開かれたこともありませんでしたので、辞任・解任の通告は納得いくものではありませんでした。私は理事長に通告の理由は何かと質問しましたが、明確な回答は一切ありませんでした。金曜日に、月曜日朝までに提出せよと言われたので、私が自覚していない重大な服務規程違反が私の側にあるのではないかと思い、学園の将来を考えて辞表を書きました。某副学長は、私のメールを無断で多方面に転送し、根拠もなく私をストーカー呼ばわりしました。その後、人事部を含め大学側に私を排除するような姿勢が見受けられました。文科省担当官によれば、理事会の了承を得ずに理事長が学長を解任した事例は、1959年に大学の敗訴事例が1例あるのみであるとのことでした。
その後、私の側に思い当たるような過失は何もないので、せめて辞表・解任にあたる証拠を示してほしいと思い、12月に地位保全の仮処分を申し立てました。その際大学側から出てきた資料は、根拠のない一部こじつけたような資料でした。同月の理事会で、辞表・解任の理由をたずねようとしたところ、ご存知のように理事長から「そのことについては裁判で述べてください」と制止されました。当時まだ名目上は2021年3月まで学長職にありましたので、仮処分は一旦取り下げ、同年7月に辞表の取り消しと名誉毀損の回復を求める本訴を開始しました。しかし裁判でも新たな説明資料はありませんでした。結局2022年3月になり、裁判所の勧めで和解に同意し、裁判は終了しました。理事長と人事部長には、裁判にかかった費用は授業料収入で支払うべきでないと伝えてあります。
また同時並行で、グローバル・コミュニケーション学部では、私の特任教授再雇用について、担当科目を割り当てないことにより特任教授に推薦しないという方針が明らかになりました。学部長・学科長が、他の2名の定年退職者は特任教授に推薦し、私だけ推薦しないとすることについて、私から、前例を変更し個人攻撃する理由をたずねましたが、教授会の席上でも合理的な説明はなく結論ありきの議論に終始したので、ハラスメント委員会に訴えました。同委員会は規程により、原則2週間以内に調査委員会を立ち上げるなどの対応策を決定することが求められていますが、このケースは10週間放置されたあと、ハラスメントにあたらないという文書で私は門前払いを通告され、質問も面会も拒絶されました。人事担当部長はこの件について、学部に一任しているとして終始質問も面会も拒否しました。このあからさまなハラスメント事例は、法律の専門家によれば、ごく最近に大学敗訴の判例が確定している再雇用拒否裁判よりさらに極端な事例と見られています。本学での裁判を含むこれら一連の事情については、その都度、文科省高等教育局に出向いて担当官に報告してあります。この件においても、私の退任後突然大幅な定員割れを抱えることになった小規模私立大学のガバナンス不全が問われています。卒業式の日に理事長に挨拶した折、このハラスメント事例について説明を求めましたが、一言も回答はありませんでした。
学園のガバナンスの現状について一言お伝えします。件の前副学長は、本年2月末になって突然、英語センター長職を辞し休職するとの報告が教授会でありました。昨春と今春、臨時執行部の局長と部長合わせて3名が相次いで早期退職しました。前副学長は、私の存在を疎んじて理事長に直訴したようですが、私が辞表を書いたあと、最高幹部が何人も早期退職したこととはつじつまが合いません。加えて、理事長就任後の5年間で、愛校心豊かな若手・中堅の卒業生職員4名を含め、合わせて20名近くの教職員が早期退職しました。2名の学長が無念の思いで退任し、3名の副学長が任期途中で辞任させられました。昨春と今春に早期退職した3名の教員は、いずれも定年まで本学で勤めると言っていた管理職経験のある幹部教員たちです。特に、理事会・評議員会のメンバーで教職員と学生から信頼の厚かったもう一人の前副学長は、辞任届の提出と契約の途中変更を強いられた末に他大学に移籍しました。教員・職員は、不穏な事態に関する説明もなされぬまま、仕事に取り組んでいます。特に教員は、本学の一年任期の契約書が特殊な文面なので、現在のガバナンス不全状態の下では、明日は我が身と不安に思うことでしょう。
理事・評議員・監事の皆様、私の副学長・学長在任中、そしてその後今まで、お気にかけていただきどうもありがとうございます。このような形で将来性豊かなこの学園を去ることになるのはまことに残念です。昨今文科省での私立学校法改正の議論にもありますように、大学ガバナンスにおいては、前例を逸脱したり契約を変えたりするような大きな変更がある場合に、十分な説明と良好なコミュニケーションが不可欠です。大学の代表者の決断は理事、評議員、監事おひとりおひとりの決断の反映でもあります。その点で今ほど皆様の役割が問われている時はありません。世界情勢の例を見てもわかるように、本学園でも、力に任せた専断を断ち切り、調和を重んじる教育の理想を求める大学の名に恥じないガバナンスを是非高めていっていただきたいと願って止みません。
以上


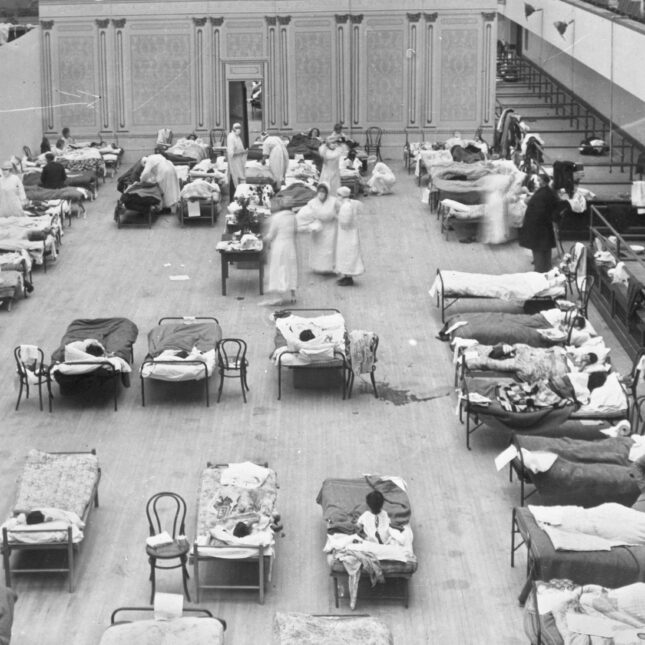


コメント